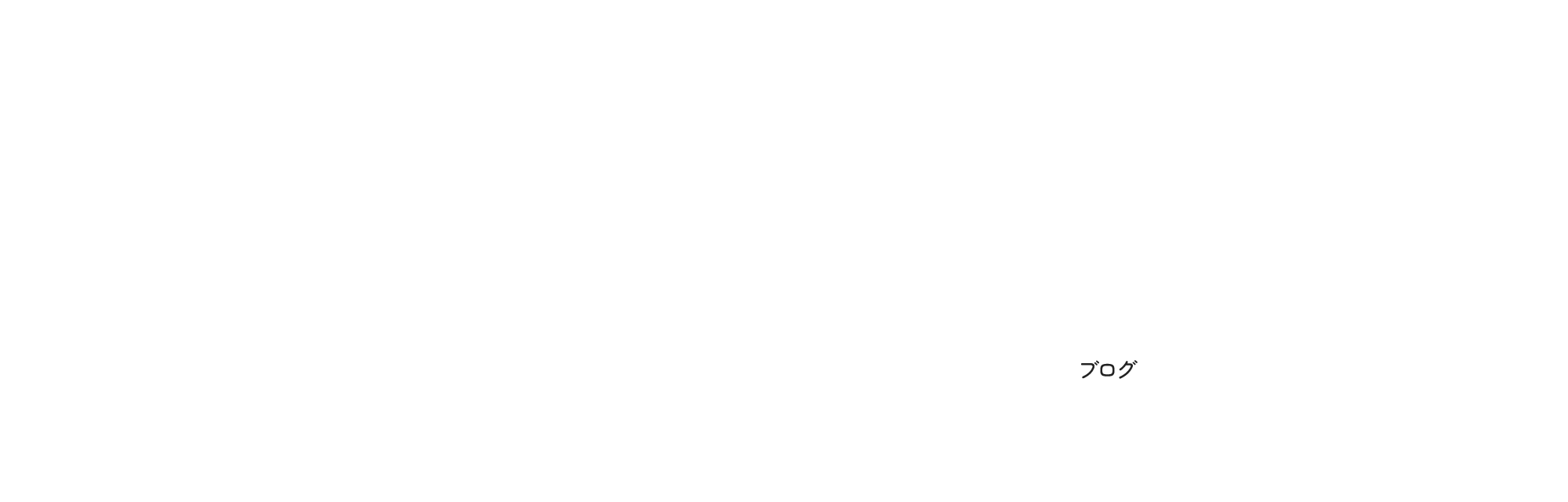
月別アーカイブ: 2025年8月
ぽのニュース~“強い精神訪問看護チーム”~
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~“強い精神訪問看護チーム”~
需要は増える一方、人手は限られる——精神訪問看護の現場を前に進める鍵は、仕組み化とチーム設計です。ここでは管理者・リーダー向けに、**臨床品質(Q)×安全(S)×生産性(P)**を同時に高める運営のコアをまとめます。🚀
1|ケアの土台:3つのフレーム 🌱
-
リカバリー志向:症状の軽減“だけ”ではなく、本人が望む生活目標を中心に。
-
トラウマ・インフォームド・ケア(TIC):安全・選択・協働・信頼・エンパワメントの5原則。
-
ハームリダクション:完全断絶を強要せず、より安全な行動を積み重ねる。
2|評価と可視化:測って支える 📊
-
標準尺度の活用:PHQ-9(抑うつ)、GAD-7(不安)、睡眠尺度、服薬アドヒアランス確認。
-
WRAP/安全計画:再発サイン・対応先・連絡順を“1枚”で。
-
訪問ゴールはSMARTに:具体・測定・達成・関連・期限。
3|リスクマネジメント:ゼロから“予防文化”へ 🛡️
-
自傷他害・自殺リスクの評価と動的見直し(週次のケースレビュー)。
-
Safety Planの実装:警戒サイン→自助→家族・支援者→専門職→救急の段階設計。
-
ハイリスク時のW訪問・頻回化、オンコール指示系統の一本化。
-
スタッフ安全:単独訪問の入退チェック、セーフワード、夜間の駐停車動線の標準化。
4|多職種連携の“リズム” 🤝📞
-
退院48時間以内の初回訪問をKPI化。
-
主治医・薬剤師・相談支援と月次ミーティング。
-
就労・就学支援(IPS等)、居住支援・地域包括との橋渡し。
-
ピア(当事者)スタッフの参画で当事者性と納得感を高める。
5|記録・情報・ICT:書きすぎず、漏れなく ✍️📱
-
音声入力+テンプレでSOAP/フォーカス記録を当日完了。
-
写真・数値はタグ統一(例:#創傷 #浮腫 #睡眠)で検索性UP。
-
機密保持:端末暗号化・二段階認証・共有範囲の最小化。
6|教育とスーパービジョン 🎓
-
90日オンボーディング:①安全計画とリスク評価 ②薬理・副作用 ③面接技法(動機づけ面接/認知行動) ④家族支援 ⑤記録と連携。
-
週次ケースレビュー×月次ケースカンファ:学びを言語化し、暗黙知を共有。
-
ことばのガイドライン:レッテルを避け、人中心の表現(“○○さんは〜という課題を抱えている”)。
7|スケジュール設計:移動を短く、関わりを濃く 🚗🗺️
-
地理クラスターと時刻スロットで訪問を束ねる。
-
ルート最適化で移動▲10–20%を目標に。
-
W訪問の先読み(新規・退院直後・急性期)で夕方の渋滞を回避。
8|KPIダッシュボード(例)📈
-
初回訪問48h達成率/再入院・再受診率/オンコール応答時間
-
記録当日完了率/安全計画整備率/服薬アドヒアランス
-
本人・家族の満足度/スタッフ離職率・オンコール負荷
9|“30日で変える”改善ロードマップ 🗺️⚙️
-
Day1–7:リスク評価票・安全計画を全ケースで更新。
-
Day8–14:訪問テンプレ・音声入力を導入して記録当日完了へ。
-
Day15–21:地理クラスターでルート再編/W訪問基準を文書化。
-
Day22–30:月次カンファでKPI振り返り→翌月の“やること一行表”に落とす。
10|ミニケース:不眠×不安の方への3週間プラン 🌙🧩
-
Week1:睡眠衛生の整え(起床時間固定・昼寝カット・就寝前ルーティン10分)
-
Week2:日中活動の“1歩”(散歩10分→15分)、思考記録で不安の整理
-
Week3:小さな成功の反復+安全計画の見直し、受診時に共有
→ **中途覚醒が1回に減少、日中のだるさ低減、外出が週3回へ。**🌟
🔴 緊急時:いのちの危険を感じる、切迫した自傷他害の兆候がある——その際は119、地域の精神科救急や緊急相談に直ちに連絡。チームは救急と連動して動きます。
まとめ ✨
“強いチーム”は、**理念(リカバリー)×技(評価・面接)×仕組み(安全・記録・KPI)**の三位一体。
小さな再現可能な仕掛けを積み上げれば、重症化の波に負けない在宅支援が実現します。
現場のテンプレ・安全計画の雛形・KPIシートなど、必要なツールはお気軽にお声がけください。🌈📩
お問い合わせは↓をタップ
ぽのニュース~“こころの看護”~
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~“こころの看護”~
病院やクリニックの時間だけでは伝えきれない不安や生活上の困りごと——それらをご自宅という安心できる場所で看護師が一緒に整えていくのが、精神訪問看護です。うつ病・双極性障害・統合失調症・不安障害・発達特性のサポート・依存からの回復期・産後のメンタルケア・高齢者の不眠やせん妄リスクの管理など、年齢を問わず幅広く伴走します。ここでははじめての方・ご家族向けに、できる支援・利用の流れ・よくある疑問をまとめました。🌿
精神訪問看護で“できること”10選 🎯
-
症状と体調の観察:睡眠・食欲・活動量・気分の波を一緒に点検。
-
お薬の相談:飲み忘れ対策、飲み合わせや副作用の気づき支援💊。
-
生活リズムづくり:起床時間/食事/入浴/外出の“小さな約束”から再スタート。
-
ストレス対処(セルフケア):呼吸法・グラウンディング・考えの整理🧘♀️。
-
危機サインの早期発見:再発のサイン表を作り、安全計画を共有。
-
家族支援:関わり方のコツ、困った時の伝え方、介護負担の調整👪。
-
通院・社会資源の連携:主治医との情報共有、福祉サービスや制度の案内。
-
就学・就労の助走:起床訓練・通勤練習・学校や職場との橋渡し🎒💼。
-
からだの病気も一緒に:生活習慣病の指標チェック、受診同行。
-
看取りを含む長期的支援:緩和ケアやグリーフケアも、必要に応じて。🕊️
目的は「病気と闘う」ではなく、その人らしい一日の再構築。小さな達成の積み重ねが回復を加速します。
利用開始までの流れ 🗺️
相談(電話・LINE・紹介) → 面談 → 主治医の指示書 → 契約&計画作成 → 初回訪問。
退院直後や症状が不安定な時は、初めの1〜2週間を手厚く(回数を増やす/W訪問)する設計が安心です。⏱️
1回の訪問はこんな感じ ⏰
-
チェックイン:今週の“よかったこと”から開始。
-
体調・薬・睡眠の確認:数値やメモを一緒に振り返り。
-
課題ワーク:呼吸法3分、家事5分、買い物の練習など小さく短く。
-
次の一歩を決める:次回までの約束を具体的に1つ。
-
家族へ報告(同意の範囲で):支援ポイントを簡潔に共有。📝
家族の“関わり方メモ” 🤝
-
してほしいことを肯定語で:「〜しないで」より「〜してくれると助かる」。
-
予定は“幅”で伝える:「9時に起きて」→「9〜10時の間に起きられたらOK」。
-
評価より観察:「ちゃんとして」ではなく「昨日より30分早く起きられたね」。
-
疲れたら休む:ケアラーにも休息日。レスパイトの情報収集を。
5分セルフケア(保存版)⏳🧘
-
4-4-4呼吸:4秒吸う→4秒止める→4秒吐く×5セット。
-
足裏グラウンディング:足の感覚に注意を向ける→床の固さ・温度を言葉に。
-
3つ探し:今見えるもの・聞こえる音・触れている物を3つずつ挙げる。
よくあるQ&A 💡
Q. どの保険が使えますか?
A. 多くは医療保険が適用、状態により**公費助成(例:自立支援医療)**の対象となる場合があります。詳細は事業所にご相談ください。
Q. 夜間は?
A. 24時間の連絡体制(オンコール)で、症状変化や不眠・不安時に電話相談が可能。緊急性に応じて臨時訪問や受診連携を行います。
Q. 何を準備すればいい?
A. お薬手帳、体温計・血圧計、最近の困りごとのメモがあるとスムーズです。
🔴 いのちの危険があると感じたら:ためらわず119、地域の精神科救急や緊急相談窓口へ。夜間・休日でも連絡してください。
まとめ ✨
精神訪問看護は、医療×生活×家族をつなぐ“在宅のセーフティネット”。
「うまく言葉にできない不調」「再発が怖い」「家族としての限界」——そんな時こそご相談ください。**“あなたらしい一日”を一緒に取り戻します。**🌙💐
お問い合わせは↓をタップ



