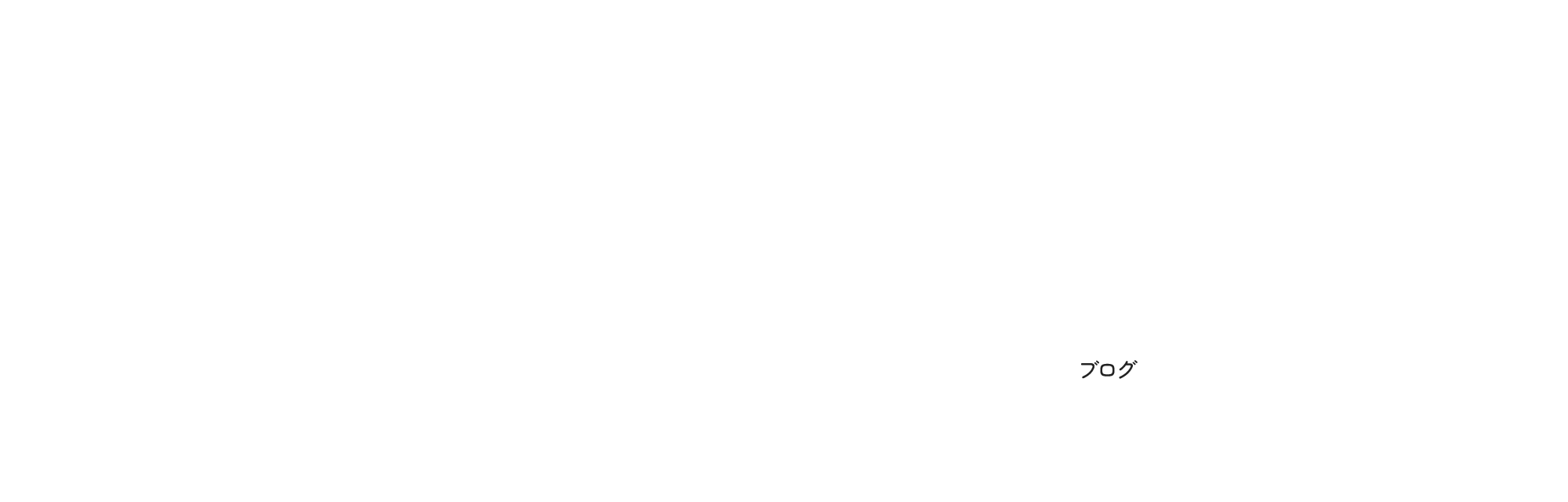
月別アーカイブ: 2025年9月
ぽのニュース~オススメのリフレッシュ法~
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~オススメのリフレッシュ法~
1|リフレッシュの基本原則(3つだけ)
-
短く・頻繁に:1回完璧より、1日3回の“小さな回復”が効く。
-
五感を使う:視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚の刺激で自律神経を整える。
-
安全と同意:体調・既往・薬の副作用を踏まえ、無理せず、イヤなことはしない。
2|時間別:1分・3分・10分・30分メニュー ⏱️
1分:超マイクロ回復
-
4-6呼吸:4秒吸って6秒吐く×6回。手のひらをお腹に当てて腹式で。
-
冷温刺激:冷たいタオルで頬を押さえる or ホットパックで肩を温める。
-
姿勢リセット:壁にもたれて後頭部・肩甲骨・お尻・かかとを“壁ピタ”で30秒。
3分:五感スイッチ
-
足裏グラウンディング:椅子に座り、足裏で床を感じる→つま先上下→かかと上下。
-
“5-4-3-2-1”:見える5つ・触れる4つ・聞こえる3つ・嗅げる2つ・味わえる1つを意識して言語化。
-
香りの一滴:ラベンダー/オレンジなどをコットンに1滴(直接皮膚は避ける)。
10分:軽運動 or クリエイティブ
-
イス・ヨガ3ポーズ:首ゆっくり回し→肩すくめ→座位の前屈。呼吸と同期。
-
リズム散歩:家の中や玄関先で“100歩カウント散歩”。
-
塗り絵・折り紙:手を動かし“できた”感を得る。
30分:深めのリセット
-
光 + 散歩:ベランダや玄関先で日光5分→近所をゆっくり20分。
-
生活リズム回復セット:洗濯物たたみ10分→水分補給→軽い片付け10分。
-
音楽浴:好きな曲3~5曲を“耳だけに集中”して聴く(ながら作業NG)。
3|症状別のコツ
不安・パニック傾向
-
吐く息長めの呼吸、冷感(保冷剤を手首に)で鎮静。
-
身体スキャン:足→ふくらはぎ→太もも…と力を入れて抜く。
-
⚠️カフェイン・刺激的ニュースは回避。
抑うつ・意欲低下
-
超小目標:ベッドから足を下ろす→洗顔→窓を開ける(3ステップでOK)。
-
朝光:カーテン全開、照度UP。
-
達成ログ:できたこと1つをスマホメモに
不眠・リズム乱れ
-
就寝90分前の“デジタル日没”:画面オフ→湯温40℃×10分の入浴→部屋暗め。
-
日中活動:昼寝は20分まで。夕方以降の仮眠はNG。
幻覚・妄想が気になる時
-
現実検討の合言葉:今“ここ”で確かな3つ(触れる物/時刻/今日の予定)。
-
音の使い分け:単純な環境音(雨音・ホワイトノイズ)で過剰刺激を遮断。
-
⚠️追及・論破は避け、安心・安全の土台づくりを優先。
強迫・ルミネーション(反芻思考)
-
タイムボックス:悩む時間を“5分”に枠取り→終わったら“行動”へ。
-
手仕事:洗い物・拭き掃除・折りたたみなど“完了感”のある単純作業。
4|おうちでできる“五感キット”の作り方
-
触覚:小さなマッサージボール/やわらかストレスボール
-
嗅覚:ラベンダー/柑橘のコットンボトル(皮膚直付けは避ける)
-
視覚:小型の自然写真カード(海・森・空)
-
聴覚:お気に入り曲の“短い”プレイリスト(3~5曲)
-
味覚:口どけよい飴/カフェインレスティー
→ 透明ポーチにまとめ、テーブル/玄関の“見える場所”へ。探さず使えるのがコツ。
5|屋外アイデア(安全第一で)♀️️
-
“家の敷地から一歩”散歩:門の外まで行って深呼吸→戻るでもOK。
-
マイクロ自然:ベランダ菜園/観葉植物の水やり。
-
目的付き外出:ポスト投函・コンビニで水購入など“1タスク”だけ。
6|家族ができる“そっと支える”声かけ例 ️
-
選択肢で促す:「今は音楽とお茶、どっちにする?」
-
具体で短く:「いま一緒に3回だけ深呼吸しよっか」
-
結果より過程を称賛:「玄関まで出たのナイス。続きはまたでOK」
-
境界も大切:「無理はしない。困ったら合言葉“ヘルプ”で」
7|訪問看護師の“現場リフレッシュ”(セルフケア)
-
入室前リセット30秒:肩すくめ→吐く息長め→“私は今ここにいる”と自分に言う。
-
退室後のデブリーフ:気づき1行メモ、感情ラベル付け(驚き/不安/安堵など)。
-
移動中の保護:ニュース/SNS断ちの“無音時間”を1区間。
-
週1の補給:同僚とケース振り返り15分、成功の要因言語化。
8|“やらない方がよいこと”チェックリスト
-
体調不良時の無理な運動・長風呂
-
断食・極端な食制限(薬の飲み方に影響)
-
アルコールでの気分転換
-
夜更かしを“ご褒美”にする
-
不快刺激(ホラー/攻撃的ニュース)を寝る前に見る
9|1週間の“軽運動+五感”サンプル計画 ️
| 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 月 | カーテン全開+深呼吸 | 100歩散歩 | 音楽3曲でクールダウン |
| 火 | 白湯1杯 | イス・ヨガ3ポーズ | 足湯10分 |
| 水 | 好きな香り1滴 | ベランダ植物チェック | 4-6呼吸×6 |
| 木 | 窓辺で日光5分 | 片付け10分 | ハーブティー |
| 金 | “できたこと”1行メモ | 郵便投函 | ストレッチ10分 |
| 土 | 軽い掃除 | 家族とお茶時間 | デジタル日没 |
| 日 | 好きな朝食 | 近所をゆっくり散歩 | 入浴→就寝前読書15分 |
10|“いざという時”のミニ危機プラン ⚠️
-
サイン:眠れない2日連続/食事2食以上抜く/不安10点満点中7以上
-
最初の一手:4-6呼吸→冷温刺激→連絡先カードを確認
-
連絡順:家族→訪問看護→主治医/クリニック→夜間窓口
-
安全:ベランダ/浴室の鍵確認、刺激になる動画/掲示は一旦オフ
11|“効いたかどうか”を見える化:超シンプル記録 ️
-
やったこと:□呼吸 □散歩 □音楽 □香り □片付け ほか
-
前の気分(0~10):____ → 後の気分:____
-
一言メモ:「夕方は音楽が合う」「朝は陽ざしで回復」など
→ 1週間で**“自分に合う時間帯・方法”**が見えてくる。
12|Q&A よくある悩み
Q. 続かない…
A. “短く・同じ時間・同じ場所”が続くコツ。朝の窓辺や歯磨き後に1分を紐づけ。
Q. 効果がわからない
A. 気分スコアを“前後で数字化”。3→5なら十分な前進!
Q. 外に出るのが怖い
A. “玄関まで”→“門まで”→“家の前5歩”の段階表を作る。達成ごとに◎をつける。
まとめ ✨
リフレッシュは「気合い」ではなく**“仕組み”**です。
-
短く頻繁に、
-
五感を使い、
-
安全と同意を大切に。
訪問看護の場だからこそ、その人の暮らしの文脈に合わせた“続く工夫”ができます。今日、このあと1分の呼吸から始めてみましょう。小さな回復の積み重ねが、再燃予防と生活満足度を着実に引き上げます
お問い合わせは↓をタップ
ぽのニュース~変遷~
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~変遷~
1|なぜ今、精神訪問看護なのか?
かつて日本の精神保健は長期入院・入所に依存しがちでした。しかし「地域移行」「地域定着」を掲げ、住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことを支える潮流が強まり、その中核として精神訪問看護が注目されてきました。訪問看護は、症状の自己管理支援、服薬アドヒアランスの支援、家族支援、危機介入、生活リズムの再構築、再入院の予防など、医療と生活の間をつなぐ橋渡しの役割を担います。
2|~1990年代:病院中心から地域の芽生えへ 🌱
-
背景:長期入院が多く、地域の受け皿は限定的。退院後の支援が細切れで、家族負担が過大になりやすい構造でした。
-
訪問看護の原型:外来看護・デイケア・作業所・グループホーム等が増え始め、**「病院の外で支える看護」**の必要性が明確に。
-
課題:症状変動の早期察知や再燃予防の「日常的モニタリング」を、医療として継続的に担う枠組みが未成熟でした。
3|2000年代:制度整備と事業化の進展 🏗️
-
診療報酬の評価が進む:精神科領域の訪問看護が制度上明確に位置づけられ、医療保険での継続支援が可能に。
-
連携の地盤作り:精神科外来・地域包括・相談支援・就労支援との多職種連携が進行。退院調整から地域定着までをシームレスにつなぐ動きが広がります。
-
事業者視点の転換:ボランタリーな「善意」に依存せず、品質と継続性を前提にした事業運営(人員配置・記録・安全管理・研修)が当たり前に。
この時期に洗練された実践の例
-
服薬セルフマネジメント支援(服用スケジュール・副作用の観察・主治医共有)
-
生活リズムの再構築(睡眠・食事・社会参加計画)
-
家族支援(負担軽減、危機時対応、関わりの工夫)
-
早期警戒サインの共有(WRAP等のリカバリープラン活用)
4|2010年代:地域移行の加速、ACT/アウトリーチの拡大 🚶♀️🤝
-
地域移行・定着の推進で、長期入院者の退院支援が加速。退院後の初期不安定期を切れ目なく支える訪問看護の需要が伸長。
-
アウトリーチの高度化:ACT(包括型地域生活支援)など、多職種チームによる積極的・継続的支援モデルが普及。危機介入、服薬調整支援、社会資源の橋渡しが一体で提供されます。
-
ピアとの協働:当事者の経験知を活かすピアサポーターと看護職が協働し、リカバリー志向(希望・強みベース)の支援計画が主流化。
5|2020年代前半:コロナ禍で再定義された“生活密着型医療” 😷➡️💡
-
面接制限と孤立リスク:通所・外来の利用が揺らぎ、家庭内での不安・生活リズムの乱れが顕在化。
-
ハイブリッド化:対面訪問を軸に、電話・オンライン面談を組み合わせたハイブリッド支援が定着。服薬確認、睡眠・気分のチェック、危機介入の初動を遠隔で繋ぎます。
-
連携のスピードアップ:医療・行政・地域資源との情報共有が高速化し、再燃兆候→初期介入→医師連絡→再安定化の流れが洗練。
6|実践の進化:ケアは“指示”から“共同の自己管理”へ 🧭
昔:服薬・受診の「指導」や「見守り」中心
今:本人と共に計画を作り、**自己管理力(Self-Management)**を育てる伴走へ
-
リカバリープラン:希望・価値・役割の明確化→週次のミニ目標設計
-
早期警戒サイン表:睡眠・食欲・思考・対人の変化を見える化
-
服薬アドヒアランス:副作用セルフモニタリング、飲み忘れ対策、医師へのフィードバック
-
危機対応プロトコル:連絡先・受診先・家族対応・安全確保手順を事前合意
-
家族支援:関わりの工夫(過干渉/放任の振り幅調整)、家族自身のセルフケア
7|人材とチームの変遷:専門性の統合とスーパービジョン 👥
-
多職種チーム:看護師・精神保健福祉士・作業療法士・薬剤師・相談支援・就労支援・住まい支援が同じ目標地図で協働。
-
ピアスタッフ:訪問帯同やグループ活動で希望のロールモデルを提示。
-
スーパービジョン:ケース検討・倫理カンファ・振り返りを定例化し、臨床推論と安全を両立。
-
バーンアウト対策:危機対応の心理的負荷に備え、デブリーフィング・EAP・勤務設計を整備。
8|テクノロジーの導入:可視化と迅速性を高める 🖥️📱
-
電子記録・モバイル入力:訪問直後に記録→チームで共有→危険サインを自動検知。
-
ダッシュボード化:入院回避率、受診遵守率、睡眠・服薬記録、社会参加回数などアウトカム指標を見える化。
-
遠隔連携:オンライン家族面談、服薬ボックスやスケジュールアプリの活用。
-
安全配慮:行先共有、SOSボタン、個人情報保護のアクセス権限管理は必須。
9|事業運営の進化:KPIと品質保証の時代 📊✅
創業〜立ち上げ期
-
医療機関・相談支援・自治体との関係構築/紹介ルートの確立
-
人材採用・教育・記録様式の標準化
拡大・安定期
-
KPI例:新規受入件数、定着率、急性増悪の未然防止率、再入院率、訪問後48h以内の記録完了率、家族面談実施率、連携会議参加率
-
品質指標:本人参加型計画率、危機プラン作成率、ピア同席率、情報共有の平均所要時間、ヒヤリハット報告率
-
教育と安全:リスクアセスメント研修、暴力リスク対応、感染対策、夜間・単独訪問ルール
10|よくある臨床テーマと最新の視点 🧩
-
統合失調症:陰性症状・認知機能の支援(日課化・小さな成功体験の積み上げ)
-
気分障害:日内変動と睡眠衛生、活動記録を用いた負荷調整
-
不安・PTSD:曝露や段階的外出の伴走、安心の合意形成
-
依存症・併存症:多機関連携と再燃予防計画、害の低減(Harm Reduction)
-
発達特性を併せ持つ場合:感覚過敏・時間管理・コミュニケーションの環境調整
-
家族支援:感情表出(EE)を下げる関わり方、**“ほどよい距離”**の設計
11|これからの展望:リカバリー×アウトカム×地域共生へ 🚀
-
本人主体のゴールを中心に、「できること」を増やす支援へ。
-
アウトカムと質の可視化:再入院率・受診遵守・生活満足度・社会参加指標・就労/就学継続などをチームで追う。
-
ハイブリッド支援の高度化:対面+遠隔で初期兆候を逃さない仕組みづくり。
-
地域共生:住まい・仕事・居場所を束ね、“医療+くらし”の統合を推進。
-
スタッフウェルビーイング:燃え尽き予防と学習文化の構築が、結果的に利用者アウトカムを最大化します。
最後に✍️
精神訪問看護は、病院の外へと医療を拡張し、地域で暮らし続ける力を支えるインフラとして進化してきました。制度の整備、チーム医療、リカバリー志向、テクノロジーの活用――そのすべてが重なり合い、今や**「再燃を防ぎ、希望に沿った暮らしを共につくる」実践へ。これからはアウトカムの可視化と働きやすい現場**が鍵。小さな改善の積み重ねが、地域の安心を大きく育てます🌈
お問い合わせは↓をタップ



