-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
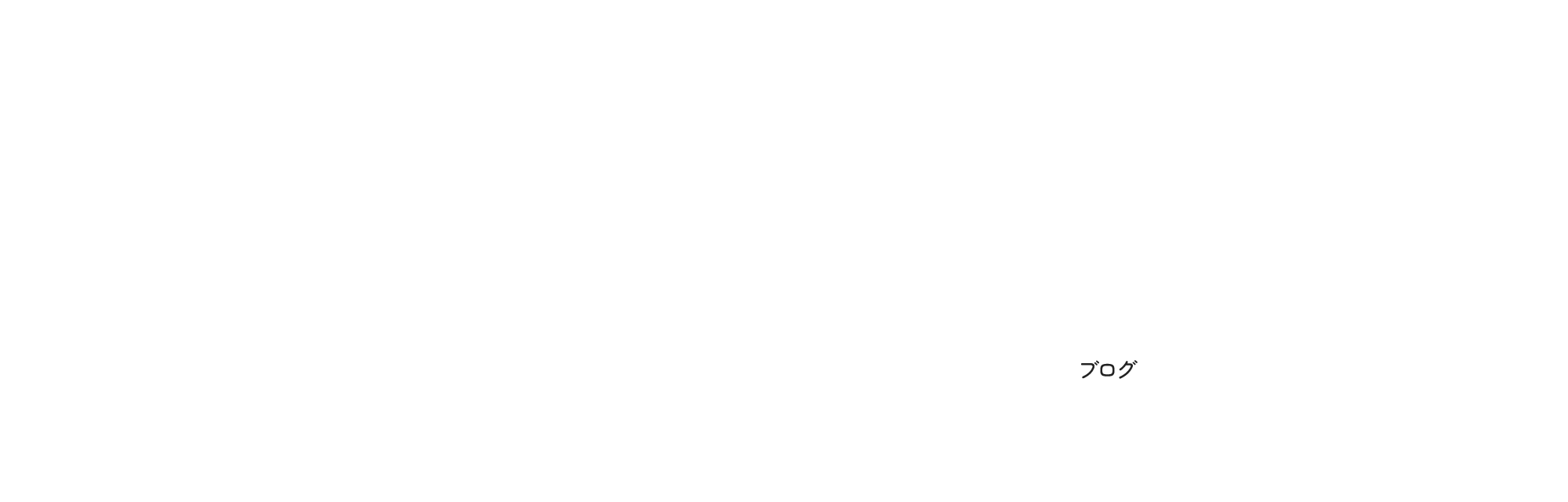
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~孤立を防ぎ、希望をつなぐ~
精神疾患を抱える方の中には、
「人と関わるのが怖い」「外に出るのがつらい」と感じる方も多くいます。
そんな方々に、そっと寄り添い、社会との“橋渡し”をするのが
精神訪問看護なんです
家の中で安心して話ができる環境だからこそ、
少しずつ心がほどけていく。
その小さな積み重ねが「希望」につながります✨
1️⃣ 安心できる居場所づくり
話をするだけでなく、相手の“気持ち”を受け止める
2️⃣ 再発予防・早期発見
体調や気分の変化をいち早く察知して医師と連携⚕️
3️⃣ 家族も支える
介護者やご家族の不安にも寄り添い、共に支援
“ひとりで抱え込まない社会”をつくるための大切な役割です
精神訪問看護は、医師・ソーシャルワーカー・福祉関係者など
多くの専門職と連携して進められます✨
チームで支えることで、
「病気を治す」から「生活を支える」へと支援の形が変わっていきます
「最初は目も合わせられなかった利用者さんが、
今では“ありがとう”と笑顔を見せてくれた」
「病気を診るだけでなく、“人”を支える。
その重みと喜びを日々感じています」
こうした一つひとつの瞬間が、看護師たちの原動力になっています✨
ストレス社会といわれる今、
心のケアは誰にとっても必要なテーマです
精神訪問看護は、
“病気を持ちながらも暮らせる社会”を実現するための大切な存在。
そして、すべての人が「安心して生きていける地域」をつくるカギなんです
小さな訪問が、大きな希望を生む。
精神訪問看護は、人と人の心をつなぐ架け橋です
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~心の回復を“家”で支える~
精神訪問看護とは、心の病気を抱える方が“自分らしく生活できるように”
看護師が自宅を訪問して支える医療サービスのことです✨
うつ病・統合失調症・双極性障害・不安障害など、
精神的な症状を抱える方は、病院だけでのサポートでは
日常生活に戻るのが難しい場合もあります😔💭
そこで頼れる存在になるのが、精神訪問看護師なんです👩⚕️💐
訪問先では、薬の管理や体調確認だけでなく、
心の状態をゆっくり丁寧に見守ります🌈
服薬のサポート💊
睡眠・食事・生活リズムのアドバイス🕊️
不安・悩みを一緒に整理する🗣️
ご家族への支援・相談も✨
「話を聞いてくれる人がいる」
——それだけで、安心できる方がたくさんいらっしゃいます🍀
自宅での訪問は、病院とは違って“ありのまま”の生活が見える場所🏡
その人らしい暮らしや、日々の小さな変化に気づけるのが大きな特徴です。
看護師がその人のペースに合わせ、
少しずつ社会とのつながりを取り戻していく。
「焦らず、ゆっくり、一歩ずつ」——
そんな優しい支援ができるのが精神訪問看護です💞
精神訪問看護は、単なる医療サービスではなく、
人の“生きる力”を支える仕事です✨
「また笑えるようになった」
「外に出てみようと思えた」
そんな言葉を聞ける瞬間が、何よりのやりがいです🌈
心をケアする医療が、もっと身近に。
精神訪問看護は、未来の地域医療を変えていきます🌿🏥
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~オススメのリフレッシュ法~
目次
短く・頻繁に:1回完璧より、1日3回の“小さな回復”が効く。
五感を使う:視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚の刺激で自律神経を整える。
安全と同意:体調・既往・薬の副作用を踏まえ、無理せず、イヤなことはしない。
4-6呼吸:4秒吸って6秒吐く×6回。手のひらをお腹に当てて腹式で。
冷温刺激:冷たいタオルで頬を押さえる or ホットパックで肩を温める。
姿勢リセット:壁にもたれて後頭部・肩甲骨・お尻・かかとを“壁ピタ”で30秒。
足裏グラウンディング:椅子に座り、足裏で床を感じる→つま先上下→かかと上下。
“5-4-3-2-1”:見える5つ・触れる4つ・聞こえる3つ・嗅げる2つ・味わえる1つを意識して言語化。
香りの一滴:ラベンダー/オレンジなどをコットンに1滴(直接皮膚は避ける)。
イス・ヨガ3ポーズ:首ゆっくり回し→肩すくめ→座位の前屈。呼吸と同期。
リズム散歩:家の中や玄関先で“100歩カウント散歩”。
塗り絵・折り紙:手を動かし“できた”感を得る。
光 + 散歩:ベランダや玄関先で日光5分→近所をゆっくり20分。
生活リズム回復セット:洗濯物たたみ10分→水分補給→軽い片付け10分。
音楽浴:好きな曲3~5曲を“耳だけに集中”して聴く(ながら作業NG)。
吐く息長めの呼吸、冷感(保冷剤を手首に)で鎮静。
身体スキャン:足→ふくらはぎ→太もも…と力を入れて抜く。
⚠️カフェイン・刺激的ニュースは回避。
超小目標:ベッドから足を下ろす→洗顔→窓を開ける(3ステップでOK)。
朝光:カーテン全開、照度UP。
達成ログ:できたこと1つをスマホメモに
就寝90分前の“デジタル日没”:画面オフ→湯温40℃×10分の入浴→部屋暗め。
日中活動:昼寝は20分まで。夕方以降の仮眠はNG。
現実検討の合言葉:今“ここ”で確かな3つ(触れる物/時刻/今日の予定)。
音の使い分け:単純な環境音(雨音・ホワイトノイズ)で過剰刺激を遮断。
⚠️追及・論破は避け、安心・安全の土台づくりを優先。
タイムボックス:悩む時間を“5分”に枠取り→終わったら“行動”へ。
手仕事:洗い物・拭き掃除・折りたたみなど“完了感”のある単純作業。
触覚:小さなマッサージボール/やわらかストレスボール
嗅覚:ラベンダー/柑橘のコットンボトル(皮膚直付けは避ける)
視覚:小型の自然写真カード(海・森・空)
聴覚:お気に入り曲の“短い”プレイリスト(3~5曲)
味覚:口どけよい飴/カフェインレスティー
→ 透明ポーチにまとめ、テーブル/玄関の“見える場所”へ。探さず使えるのがコツ。
“家の敷地から一歩”散歩:門の外まで行って深呼吸→戻るでもOK。
マイクロ自然:ベランダ菜園/観葉植物の水やり。
目的付き外出:ポスト投函・コンビニで水購入など“1タスク”だけ。
選択肢で促す:「今は音楽とお茶、どっちにする?」
具体で短く:「いま一緒に3回だけ深呼吸しよっか」
結果より過程を称賛:「玄関まで出たのナイス。続きはまたでOK」
境界も大切:「無理はしない。困ったら合言葉“ヘルプ”で」
入室前リセット30秒:肩すくめ→吐く息長め→“私は今ここにいる”と自分に言う。
退室後のデブリーフ:気づき1行メモ、感情ラベル付け(驚き/不安/安堵など)。
移動中の保護:ニュース/SNS断ちの“無音時間”を1区間。
週1の補給:同僚とケース振り返り15分、成功の要因言語化。
体調不良時の無理な運動・長風呂
断食・極端な食制限(薬の飲み方に影響)
アルコールでの気分転換
夜更かしを“ご褒美”にする
不快刺激(ホラー/攻撃的ニュース)を寝る前に見る
| 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 月 | カーテン全開+深呼吸 | 100歩散歩 | 音楽3曲でクールダウン |
| 火 | 白湯1杯 | イス・ヨガ3ポーズ | 足湯10分 |
| 水 | 好きな香り1滴 | ベランダ植物チェック | 4-6呼吸×6 |
| 木 | 窓辺で日光5分 | 片付け10分 | ハーブティー |
| 金 | “できたこと”1行メモ | 郵便投函 | ストレッチ10分 |
| 土 | 軽い掃除 | 家族とお茶時間 | デジタル日没 |
| 日 | 好きな朝食 | 近所をゆっくり散歩 | 入浴→就寝前読書15分 |
サイン:眠れない2日連続/食事2食以上抜く/不安10点満点中7以上
最初の一手:4-6呼吸→冷温刺激→連絡先カードを確認
連絡順:家族→訪問看護→主治医/クリニック→夜間窓口
安全:ベランダ/浴室の鍵確認、刺激になる動画/掲示は一旦オフ
やったこと:□呼吸 □散歩 □音楽 □香り □片付け ほか
前の気分(0~10):____ → 後の気分:____
一言メモ:「夕方は音楽が合う」「朝は陽ざしで回復」など
→ 1週間で**“自分に合う時間帯・方法”**が見えてくる。
Q. 続かない…
A. “短く・同じ時間・同じ場所”が続くコツ。朝の窓辺や歯磨き後に1分を紐づけ。
Q. 効果がわからない
A. 気分スコアを“前後で数字化”。3→5なら十分な前進!
Q. 外に出るのが怖い
A. “玄関まで”→“門まで”→“家の前5歩”の段階表を作る。達成ごとに◎をつける。
リフレッシュは「気合い」ではなく**“仕組み”**です。
短く頻繁に、
五感を使い、
安全と同意を大切に。
訪問看護の場だからこそ、その人の暮らしの文脈に合わせた“続く工夫”ができます。今日、このあと1分の呼吸から始めてみましょう。小さな回復の積み重ねが、再燃予防と生活満足度を着実に引き上げます
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~変遷~
目次
かつて日本の精神保健は長期入院・入所に依存しがちでした。しかし「地域移行」「地域定着」を掲げ、住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことを支える潮流が強まり、その中核として精神訪問看護が注目されてきました。訪問看護は、症状の自己管理支援、服薬アドヒアランスの支援、家族支援、危機介入、生活リズムの再構築、再入院の予防など、医療と生活の間をつなぐ橋渡しの役割を担います。
背景:長期入院が多く、地域の受け皿は限定的。退院後の支援が細切れで、家族負担が過大になりやすい構造でした。
訪問看護の原型:外来看護・デイケア・作業所・グループホーム等が増え始め、**「病院の外で支える看護」**の必要性が明確に。
課題:症状変動の早期察知や再燃予防の「日常的モニタリング」を、医療として継続的に担う枠組みが未成熟でした。
診療報酬の評価が進む:精神科領域の訪問看護が制度上明確に位置づけられ、医療保険での継続支援が可能に。
連携の地盤作り:精神科外来・地域包括・相談支援・就労支援との多職種連携が進行。退院調整から地域定着までをシームレスにつなぐ動きが広がります。
事業者視点の転換:ボランタリーな「善意」に依存せず、品質と継続性を前提にした事業運営(人員配置・記録・安全管理・研修)が当たり前に。
この時期に洗練された実践の例
服薬セルフマネジメント支援(服用スケジュール・副作用の観察・主治医共有)
生活リズムの再構築(睡眠・食事・社会参加計画)
家族支援(負担軽減、危機時対応、関わりの工夫)
早期警戒サインの共有(WRAP等のリカバリープラン活用)
地域移行・定着の推進で、長期入院者の退院支援が加速。退院後の初期不安定期を切れ目なく支える訪問看護の需要が伸長。
アウトリーチの高度化:ACT(包括型地域生活支援)など、多職種チームによる積極的・継続的支援モデルが普及。危機介入、服薬調整支援、社会資源の橋渡しが一体で提供されます。
ピアとの協働:当事者の経験知を活かすピアサポーターと看護職が協働し、リカバリー志向(希望・強みベース)の支援計画が主流化。
面接制限と孤立リスク:通所・外来の利用が揺らぎ、家庭内での不安・生活リズムの乱れが顕在化。
ハイブリッド化:対面訪問を軸に、電話・オンライン面談を組み合わせたハイブリッド支援が定着。服薬確認、睡眠・気分のチェック、危機介入の初動を遠隔で繋ぎます。
連携のスピードアップ:医療・行政・地域資源との情報共有が高速化し、再燃兆候→初期介入→医師連絡→再安定化の流れが洗練。
昔:服薬・受診の「指導」や「見守り」中心
今:本人と共に計画を作り、**自己管理力(Self-Management)**を育てる伴走へ
リカバリープラン:希望・価値・役割の明確化→週次のミニ目標設計
早期警戒サイン表:睡眠・食欲・思考・対人の変化を見える化
服薬アドヒアランス:副作用セルフモニタリング、飲み忘れ対策、医師へのフィードバック
危機対応プロトコル:連絡先・受診先・家族対応・安全確保手順を事前合意
家族支援:関わりの工夫(過干渉/放任の振り幅調整)、家族自身のセルフケア
多職種チーム:看護師・精神保健福祉士・作業療法士・薬剤師・相談支援・就労支援・住まい支援が同じ目標地図で協働。
ピアスタッフ:訪問帯同やグループ活動で希望のロールモデルを提示。
スーパービジョン:ケース検討・倫理カンファ・振り返りを定例化し、臨床推論と安全を両立。
バーンアウト対策:危機対応の心理的負荷に備え、デブリーフィング・EAP・勤務設計を整備。
電子記録・モバイル入力:訪問直後に記録→チームで共有→危険サインを自動検知。
ダッシュボード化:入院回避率、受診遵守率、睡眠・服薬記録、社会参加回数などアウトカム指標を見える化。
遠隔連携:オンライン家族面談、服薬ボックスやスケジュールアプリの活用。
安全配慮:行先共有、SOSボタン、個人情報保護のアクセス権限管理は必須。
創業〜立ち上げ期
医療機関・相談支援・自治体との関係構築/紹介ルートの確立
人材採用・教育・記録様式の標準化
拡大・安定期
KPI例:新規受入件数、定着率、急性増悪の未然防止率、再入院率、訪問後48h以内の記録完了率、家族面談実施率、連携会議参加率
品質指標:本人参加型計画率、危機プラン作成率、ピア同席率、情報共有の平均所要時間、ヒヤリハット報告率
教育と安全:リスクアセスメント研修、暴力リスク対応、感染対策、夜間・単独訪問ルール
統合失調症:陰性症状・認知機能の支援(日課化・小さな成功体験の積み上げ)
気分障害:日内変動と睡眠衛生、活動記録を用いた負荷調整
不安・PTSD:曝露や段階的外出の伴走、安心の合意形成
依存症・併存症:多機関連携と再燃予防計画、害の低減(Harm Reduction)
発達特性を併せ持つ場合:感覚過敏・時間管理・コミュニケーションの環境調整
家族支援:感情表出(EE)を下げる関わり方、**“ほどよい距離”**の設計
本人主体のゴールを中心に、「できること」を増やす支援へ。
アウトカムと質の可視化:再入院率・受診遵守・生活満足度・社会参加指標・就労/就学継続などをチームで追う。
ハイブリッド支援の高度化:対面+遠隔で初期兆候を逃さない仕組みづくり。
地域共生:住まい・仕事・居場所を束ね、“医療+くらし”の統合を推進。
スタッフウェルビーイング:燃え尽き予防と学習文化の構築が、結果的に利用者アウトカムを最大化します。
精神訪問看護は、病院の外へと医療を拡張し、地域で暮らし続ける力を支えるインフラとして進化してきました。制度の整備、チーム医療、リカバリー志向、テクノロジーの活用――そのすべてが重なり合い、今や**「再燃を防ぎ、希望に沿った暮らしを共につくる」実践へ。これからはアウトカムの可視化と働きやすい現場**が鍵。小さな改善の積み重ねが、地域の安心を大きく育てます🌈
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~“強い精神訪問看護チーム”~
需要は増える一方、人手は限られる——精神訪問看護の現場を前に進める鍵は、仕組み化とチーム設計です。ここでは管理者・リーダー向けに、**臨床品質(Q)×安全(S)×生産性(P)**を同時に高める運営のコアをまとめます。🚀
目次
リカバリー志向:症状の軽減“だけ”ではなく、本人が望む生活目標を中心に。
トラウマ・インフォームド・ケア(TIC):安全・選択・協働・信頼・エンパワメントの5原則。
ハームリダクション:完全断絶を強要せず、より安全な行動を積み重ねる。
標準尺度の活用:PHQ-9(抑うつ)、GAD-7(不安)、睡眠尺度、服薬アドヒアランス確認。
WRAP/安全計画:再発サイン・対応先・連絡順を“1枚”で。
訪問ゴールはSMARTに:具体・測定・達成・関連・期限。
自傷他害・自殺リスクの評価と動的見直し(週次のケースレビュー)。
Safety Planの実装:警戒サイン→自助→家族・支援者→専門職→救急の段階設計。
ハイリスク時のW訪問・頻回化、オンコール指示系統の一本化。
スタッフ安全:単独訪問の入退チェック、セーフワード、夜間の駐停車動線の標準化。
退院48時間以内の初回訪問をKPI化。
主治医・薬剤師・相談支援と月次ミーティング。
就労・就学支援(IPS等)、居住支援・地域包括との橋渡し。
ピア(当事者)スタッフの参画で当事者性と納得感を高める。
音声入力+テンプレでSOAP/フォーカス記録を当日完了。
写真・数値はタグ統一(例:#創傷 #浮腫 #睡眠)で検索性UP。
機密保持:端末暗号化・二段階認証・共有範囲の最小化。
90日オンボーディング:①安全計画とリスク評価 ②薬理・副作用 ③面接技法(動機づけ面接/認知行動) ④家族支援 ⑤記録と連携。
週次ケースレビュー×月次ケースカンファ:学びを言語化し、暗黙知を共有。
ことばのガイドライン:レッテルを避け、人中心の表現(“○○さんは〜という課題を抱えている”)。
地理クラスターと時刻スロットで訪問を束ねる。
ルート最適化で移動▲10–20%を目標に。
W訪問の先読み(新規・退院直後・急性期)で夕方の渋滞を回避。
初回訪問48h達成率/再入院・再受診率/オンコール応答時間
記録当日完了率/安全計画整備率/服薬アドヒアランス
本人・家族の満足度/スタッフ離職率・オンコール負荷
Day1–7:リスク評価票・安全計画を全ケースで更新。
Day8–14:訪問テンプレ・音声入力を導入して記録当日完了へ。
Day15–21:地理クラスターでルート再編/W訪問基準を文書化。
Day22–30:月次カンファでKPI振り返り→翌月の“やること一行表”に落とす。
Week1:睡眠衛生の整え(起床時間固定・昼寝カット・就寝前ルーティン10分)
Week2:日中活動の“1歩”(散歩10分→15分)、思考記録で不安の整理
Week3:小さな成功の反復+安全計画の見直し、受診時に共有
→ **中途覚醒が1回に減少、日中のだるさ低減、外出が週3回へ。**🌟
🔴 緊急時:いのちの危険を感じる、切迫した自傷他害の兆候がある——その際は119、地域の精神科救急や緊急相談に直ちに連絡。チームは救急と連動して動きます。
“強いチーム”は、**理念(リカバリー)×技(評価・面接)×仕組み(安全・記録・KPI)**の三位一体。
小さな再現可能な仕掛けを積み上げれば、重症化の波に負けない在宅支援が実現します。
現場のテンプレ・安全計画の雛形・KPIシートなど、必要なツールはお気軽にお声がけください。🌈📩
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
~“こころの看護”~
病院やクリニックの時間だけでは伝えきれない不安や生活上の困りごと——それらをご自宅という安心できる場所で看護師が一緒に整えていくのが、精神訪問看護です。うつ病・双極性障害・統合失調症・不安障害・発達特性のサポート・依存からの回復期・産後のメンタルケア・高齢者の不眠やせん妄リスクの管理など、年齢を問わず幅広く伴走します。ここでははじめての方・ご家族向けに、できる支援・利用の流れ・よくある疑問をまとめました。🌿
目次
症状と体調の観察:睡眠・食欲・活動量・気分の波を一緒に点検。
お薬の相談:飲み忘れ対策、飲み合わせや副作用の気づき支援💊。
生活リズムづくり:起床時間/食事/入浴/外出の“小さな約束”から再スタート。
ストレス対処(セルフケア):呼吸法・グラウンディング・考えの整理🧘♀️。
危機サインの早期発見:再発のサイン表を作り、安全計画を共有。
家族支援:関わり方のコツ、困った時の伝え方、介護負担の調整👪。
通院・社会資源の連携:主治医との情報共有、福祉サービスや制度の案内。
就学・就労の助走:起床訓練・通勤練習・学校や職場との橋渡し🎒💼。
からだの病気も一緒に:生活習慣病の指標チェック、受診同行。
看取りを含む長期的支援:緩和ケアやグリーフケアも、必要に応じて。🕊️
目的は「病気と闘う」ではなく、その人らしい一日の再構築。小さな達成の積み重ねが回復を加速します。
相談(電話・LINE・紹介) → 面談 → 主治医の指示書 → 契約&計画作成 → 初回訪問。
退院直後や症状が不安定な時は、初めの1〜2週間を手厚く(回数を増やす/W訪問)する設計が安心です。⏱️
チェックイン:今週の“よかったこと”から開始。
体調・薬・睡眠の確認:数値やメモを一緒に振り返り。
課題ワーク:呼吸法3分、家事5分、買い物の練習など小さく短く。
次の一歩を決める:次回までの約束を具体的に1つ。
家族へ報告(同意の範囲で):支援ポイントを簡潔に共有。📝
してほしいことを肯定語で:「〜しないで」より「〜してくれると助かる」。
予定は“幅”で伝える:「9時に起きて」→「9〜10時の間に起きられたらOK」。
評価より観察:「ちゃんとして」ではなく「昨日より30分早く起きられたね」。
疲れたら休む:ケアラーにも休息日。レスパイトの情報収集を。
4-4-4呼吸:4秒吸う→4秒止める→4秒吐く×5セット。
足裏グラウンディング:足の感覚に注意を向ける→床の固さ・温度を言葉に。
3つ探し:今見えるもの・聞こえる音・触れている物を3つずつ挙げる。
Q. どの保険が使えますか?
A. 多くは医療保険が適用、状態により**公費助成(例:自立支援医療)**の対象となる場合があります。詳細は事業所にご相談ください。
Q. 夜間は?
A. 24時間の連絡体制(オンコール)で、症状変化や不眠・不安時に電話相談が可能。緊急性に応じて臨時訪問や受診連携を行います。
Q. 何を準備すればいい?
A. お薬手帳、体温計・血圧計、最近の困りごとのメモがあるとスムーズです。
🔴 いのちの危険があると感じたら:ためらわず119、地域の精神科救急や緊急相談窓口へ。夜間・休日でも連絡してください。
精神訪問看護は、医療×生活×家族をつなぐ“在宅のセーフティネット”。
「うまく言葉にできない不調」「再発が怖い」「家族としての限界」——そんな時こそご相談ください。**“あなたらしい一日”を一緒に取り戻します。**🌙💐
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
目次
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、「精神訪問看護って実際にどんな風に動いているの?」という疑問にお応えすべく、私たち精神訪問看護師の1日の流れをご紹介します。病院勤務の看護とはまた違ったスタイルで、地域に根ざした支援を行っている様子を、少しだけのぞいてみてください。
朝は、スタッフみんなでのチームミーティングから始まります。その日に訪問する利用者様の確認や、体調の変化、支援内容の共有などを行い、必要な情報をしっかり整理します。
この時間がとても大切。なぜなら、訪問先ごとに支援内容が違うため、事前の準備や情報共有がスムーズな支援につながるからです。
訪問に必要な書類や服薬の確認表、時にはお薬や衛生用品なども持って、いざ出発です。
午前中は、おおよそ2~3件の訪問を行います。利用者様の状態や支援内容に応じて、1件あたり30分~1時間ほどかけて支援します。
たとえば──
ある方には、服薬の確認と体調チェック。生活リズムの崩れがないかも併せて確認します。
別の方には、最近の困りごとをお聞きしながら、不安への対処法やストレスケアのお話を。
引きこもりがちだった方には、少し外に出るきっかけ作りとして、近所の散歩に付き添うこともあります。
訪問は“その人の生活に寄り添う”という意味で、まさに十人十色。マニュアル通りにはいかないぶん、柔軟な対応力と相手を理解する姿勢が大切です。
お昼頃にはいったん事務所に戻ります。昼食を取りながら、午前中の記録をまとめたり、午後の準備をしたりする時間です。
訪問中に気づいたことや利用者様のちょっとした変化も、チームで共有できるようにメモしておきます。こうした“ちょっとした一言”が、後の支援につながることもあるのです。
午後も引き続き、2~3件の訪問を行います。午後の訪問では、外来や他機関との連携が必要なケースもあり、地域の支援ネットワークと協力しながら支援を進めることもあります。
また、医師やケアマネジャー、福祉施設などと連絡を取り合いながら、「この方にはどんな支援が必要か」を一緒に考えることも大切な仕事のひとつです。
すべての訪問が終わったら、事務所に戻り、その日の記録をまとめます。カルテ入力や次回訪問の調整、必要な連絡事項を整理したら、最後にチームで1日の振り返りを行います。
「今日○○さん、ちょっと元気なかったね」
「次回はこんな支援を試してみたい」
そんなやり取りを通して、よりよい支援につなげています。
精神訪問看護は、時に地道で、すぐに成果が見える仕事ではないかもしれません。でも、利用者様の「今日は話せてよかった」「ありがとう、来てくれて安心した」という言葉が、私たちのエネルギーの源です。
これからも、ひとりひとりの暮らしと心に寄り添いながら、私たちは地域を走り続けていきます。
訪問看護ステーションぽのでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
目次
「精神訪問看護って、具体的にどんなことをしているの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。今回のブログでは、精神訪問看護の基本的な役割と、その特徴について、できるだけわかりやすくご紹介します。
精神訪問看護は、うつ病や統合失調症、双極性障害、不安障害など、精神的な症状やこころの不調を抱えながら地域で生活されている方々のもとへ、看護師や精神保健福祉士などの専門職が訪問してサポートを行う医療サービスです。
病院に通うのが難しかったり、日常生活に不安を感じていたりする方にとって、自宅にいながら支援が受けられるのはとても心強いですよね。
訪問での支援内容は、その方の状態や生活スタイルに合わせて多岐にわたります。例えばこんなことを行っています。
服薬の管理と確認
「薬を飲み忘れていないか?」「副作用は出ていないか?」など、服薬の状況を確認しながら、必要に応じて主治医と連携します。
症状の観察と相談
ご本人の気分や体調、普段と違う様子がないかなどを見守り、早めに変化に気づけるようサポートします。
日常生活の支援
生活リズムを整えるお手伝いをしたり、掃除や食事、金銭管理のアドバイスを行ったりと、暮らしに直結した支援も大切にしています。
不安や悩みごとの傾聴・相談
「誰かに話を聞いてほしい」という時にも、安心して頼れる存在であることを目指しています。
精神訪問看護の大きな特徴は、“生活の場で支援を行う”ということ。病院では見えにくい、その人らしい暮らし方や環境を尊重しながら、支援を行える点が最大の魅力です。
通院に不安がある方、再発を防ぎたい方、日々の暮らしの中で悩みを抱えている方などにとって、訪問看護は「相談できる誰かがいる」安心を届ける役割を果たしています。
精神訪問看護は、医師の指示書があれば利用できる医療サービスです。診断名に関係なく、「生活に困っている」「一人での通院が難しい」「家で落ち着いて過ごしたい」と感じている方が対象です。
気になる方は、まずは主治医や担当の相談員にご相談いただくと、スムーズにご案内できます。
精神訪問看護は、病気と向き合いながらも「その人らしい生活」を支えるためのサービスです。
「誰かに少し手伝ってほしい」
「身近に相談できる人がほしい」
そんな気持ちを抱えている方が、地域で自分らしく暮らせるよう、私たちはそっと寄り添っていきます。
訪問看護ステーションぽのでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
さて今回は
~それぞれの特徴~
ということで、これら精神疾患に共通する主な特徴を通じて、当事者への理解と支援の視点を深く掘り下げていきます。
精神疾患とは、単なる気分の落ち込みや気分屋ではなく、脳の機能障害や心理的要因により、思考・感情・行動に困難をきたす病気です。代表的なものにはうつ病、統合失調症、双極性障がい、不安障がい、PTSD、強迫性障がいなどがあります。
目次
手足が動かない、血が出ているといった目に見える症状はない
周囲からは「元気そう」「普通に見える」と誤解されやすい
本人も無理して“平常を装う”傾向がある
この不可視性こそが、誤解・偏見・孤立を生む最大の原因になっています。
日によって体調・気分・認知力が大きく変化
ある日は外出できても、翌日は布団から出られないことも
同じ診断名でも、症状や生活への影響は人によって異なる
つまり、「この病気の人はこうだ」と一概に判断できないのが精神疾患の本質です。
失敗を過剰に反省し、自分を責め続けてしまう
「自分のせいで迷惑をかけている」「生きていてはいけない」といった思考に陥る
他者に頼ることができず、孤立を深めてしまう
これらは意志の弱さではなく、病の影響による思考の歪みなのです。
集中力の低下、対人関係の疲弊、突発的な体調不良
職場や学校の理解不足により「甘え」「怠慢」と受け取られることも
制度はあっても、社会の仕組みが“健康前提”で動いている
この“構造的ハードル”が、精神疾患のある人をさらに苦しめる要因となっています。
薬物療法・心理療法・生活支援など、治療には時間がかかる
回復と再発を繰り返す「慢性疾患」としての性質も
本人や家族に“継続的な理解と支援”が必要不可欠
焦らず、「支えることをあきらめない」社会的まなざしが重要です。
誰かに“理解されている”という実感が回復を後押しする
「励ましすぎる」「否定する」などの言動は悪化の原因にも
相手を“コントロール”せず、“寄り添う”姿勢が求められる
つまり、治療者だけでなく、家族や職場、地域も「治療の一部」なのです。
精神疾患は、目に見えず、理解されにくいがゆえに、当事者を二重三重に苦しめてきた歴史があります。しかし、その特性を正しく理解することで、共に生きる道は必ず開けます。
訪問看護ステーションぽのでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは。
【訪問看護ステーションぽの】の更新担当の中西です。
さて今回は
~社会保障制度~
ということで、精神疾患と向き合う方々を支える制度の仕組み、課題、そして今後の方向性について深く掘り下げていきます。
うつ病、統合失調症、不安障がい、双極性障がいなど、精神疾患を抱える人は年々増加傾向にあります。精神疾患は「目に見えにくい障害」であるがゆえに、理解されにくく、社会参加に困難を抱えることもしばしばです。そんな中で、社会保障制度は当事者の生活を支える大切な“セーフティネット”です。
目次
精神疾患を有する患者数:約600万人(厚労省推計)
中でもうつ病や不安障害は20~40代に多く、就労や学業継続に影響
「怠けている」「甘えている」という誤解
障害の“見えにくさ”からくる支援の行き届きにくさ
だからこそ、制度の活用は「生きやすさ」を手に入れる重要な手段なのです。
精神障がいの等級(1~3級)に応じて交付される
各種割引(公共交通機関、携帯電話、税金軽減)を受けられる
就労支援や福祉サービス利用時の“証明書”としての役割も大きい
障がい基礎年金・障がい厚生年金があり、生活支援の柱となる制度
初診日と保険加入要件、障害認定日の状態によって支給の可否が決まる
精神疾患による就労困難な場合の「生活保障」の一助に
通院医療費が1割負担に軽減される制度(所得に応じて上限設定あり)
精神科通院にかかる負担が大幅に軽減され、治療継続を後押し
訓練・職業紹介を通じて社会復帰を目指す
利用者の能力や病状に応じた柔軟な支援プランが用意されている
精神疾患のある方自身やその家族が「制度の存在を知らない」ケースが多い
医療機関や福祉窓口での情報提供が不十分な場合も
手続きの煩雑さや、症状による判断能力の低下が申請の障害に
精神疾患特有の「変動的な症状」が認定に影響することも
職場や教育現場でのスティグマ(負の烙印)
制度利用者に対する「逆差別」といった誤解
昔は「隔離・保護」が重視されたが、近年は「地域生活への移行支援」へ
精神疾患は「治療すべき病」であるとともに「共に生きる障がい」へと再定義されつつある
精神障がいも「障がい者差別解消法」の対象に
学校教育・企業研修でのメンタルヘルスリテラシー向上も期待
制度は重要ですが、それ以上に求められるのは「社会全体の理解」です。
障害者本人の“語る力”の尊重
家族・支援者の「寄り添い方」の見直し
医療・福祉・行政・地域が連携する“複合支援体制”
精神疾患のある人も、そうでない人も、誰もが安心して生きられる社会へ。その第一歩が、制度を知ることです。
精神疾患を抱えて生きることは、容易ではありません。しかし、日本には支援制度があり、それを正しく知り、活用することで「生きる力」を手にすることができます。
訪問看護ステーションぽのでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
お問い合わせは↓をタップ